長年、「カウンターでの対面販売」を絶対的な価値としてきたアルビオンが、2026年4月、ついに公式ECに踏み込みます。
この動きを「時代に合わせただけ」「便利になった」という一言で片付けてしまうのは簡単ですが、実はこの決断は、日本の化粧品業界が抱える構造的な変化を象徴する出来事でもあります。
注目すべきなのは、アルビオンが業績不振に追い込まれていたわけではないという点です。では、なぜ今だったのでしょうか。
売上も利益も堅調だったアルビオン
まず前提として、アルビオンの業績は直近数年、回復基調にあります。
2024年12月期の売上高は約600億円規模、営業利益も70億円超と、コロナ禍からの立ち直りは鮮明です。少なくとも「売れなくなったからECに逃げた」という構図ではありません。
それにもかかわらず、同社はこれまで守ってきた「ECを持たない」という流通哲学を転換しました。
「売れない不安」ではなく「続かない不安」
アルビオンが直面していたのは、短期的な売上減少ではなく、中長期での持続性に対する不安です。
対面販売モデルは、深いカウンセリングや関係構築に強みがあります。一方で、その価値は「来店できる顧客」にしか届きません。
顧客が年齢を重ね店頭に出向けない、生活圏や子育てなどによるライフスタイルの変化によって百貨店へ足を運べなくなるなど、どれほどブランドへの信頼があっても「買い続けられない」ケースが増えていきます。
つまり問題は「気持ちが離れること」ではなく、「物理的に続けられなくなること」でした。
BAモデルが抱える、〝見えやすさ〟の限界
もう一つ無視できないのが、BA(ビューティーアドバイザー)中心の販売モデルの構造的課題です。
アルビオンは元々制度品メーカー(自社商品を企画、生産、販売まで管理し、契約した小売店に直接販売する化粧品メーカーのこと)であることから、卸先の小売店の管理・把握はできていたものの、その先の顧客に対するアプローチができていなかった部分が課題点だと、アルビオン関係者があるインタビュー語っています。
そのため、対面販売では、「誰が売ったか」「どの提案が効いたか」が個人に帰属しやすく、データとして蓄積されにくい傾向がありました。これは人の力を最大化する一方で、組織としての再現性や分析力を高めにくいという側面も持ちます。
ECやCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)を通じて購買データを統合しなければ、顧客の変化を定量的に捉えることができない。この「データを持てない不安」という点も、判断を後押しした要因の一つでしょう。
アルビオンのECは「売るため」ではない
今回のEC参入で特徴的なのは、アルビオンがECを主戦場に据えていない点です。
公式オンラインストアは、OMO(Online Merges with Offlin:オンラインとオフラインの融合)の一環であり、顧客を〝つなぎ止める〟ための手段として位置づけられています。
会員制度やポイント連携を通じて、オンラインと店舗の行き来を可視化し、顧客理解を深める。
ECは「売上を伸ばすための武器」というより、「顧客との関係を長く保つためのインフラ」に近い役割を担っていると言えます。
これはアルビオンだけの話ではない
アルビオンの決断は、特定のブランドの戦略転換にとどまりません。
百貨店流通、対面接客、価格帯の高いスキンケア──こうした要素に支えられてきた日本の化粧品ブランド全体が、同じ問いに直面しています。
「カウンター文化を守ること」と「顧客とつながり続けること」は、必ずしも同義ではなくなってきました。
アルビオンのEC解禁は、その現実を静かに、しかしはっきりと示しています。
EC参入は妥協ではなく、思想の更新
アルビオンがECに踏み込んだ理由は、「時代に負けたから」ではありません。
むしろ、これまで築いてきた価値をこれからも成立させ続けるための更新だったと言えます。
対面販売か、ECか。
その二択ではなく、「どうすれば顧客と長く関係を続けられるか」。
その問いに、アルビオンなりの答えを出した結果が、今回のEC参入なのです。

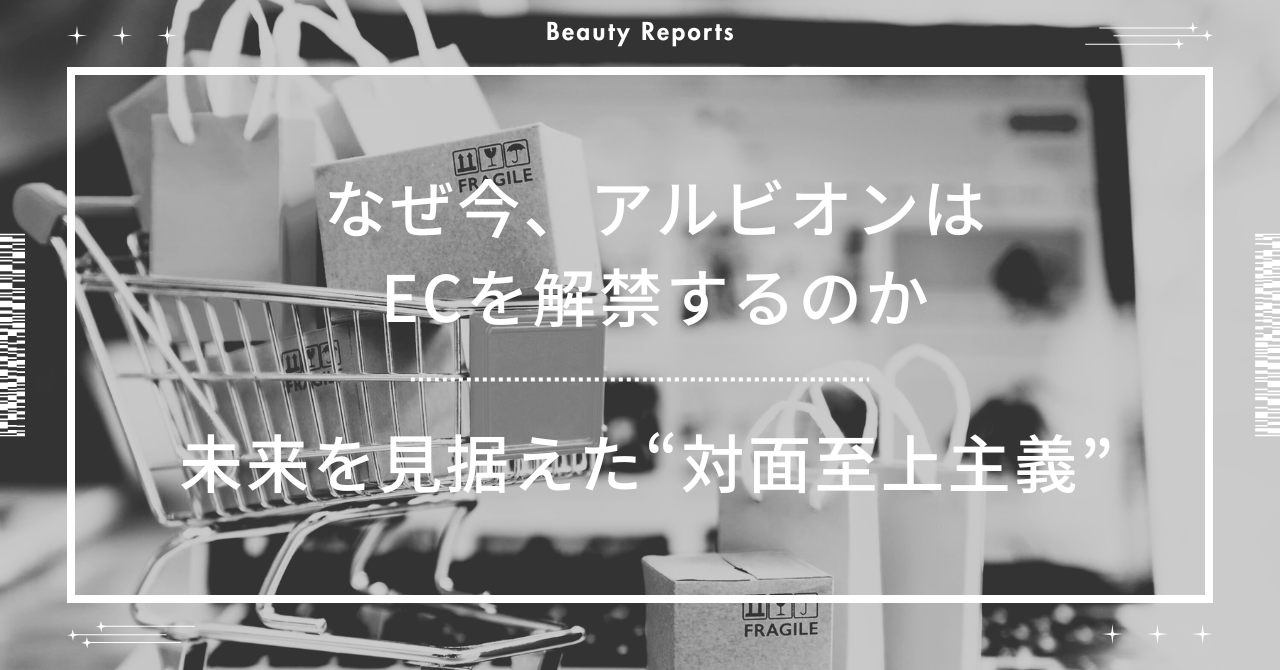

コメント